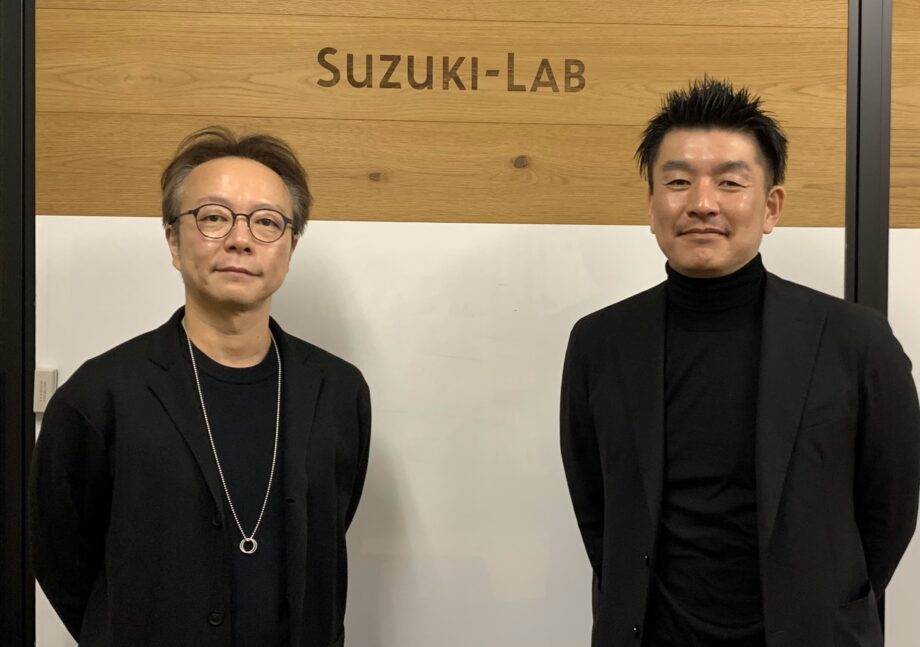INTERVIEW
起業家
【 株式会社VitroVo 】 iPS細胞×最先端技術で動物実験に頼らない創薬を実現 〜 医薬開発を加速する大学発ベンチャーVitroVoの技術と挑戦〜
#バイオ #大学発スタートアップ

新しい薬を開発するには、多くの時間とコストがかかります。これまで、薬の安全性や効果を確かめるためには、試験管内での実験(in vitro)と動物実験(in vivo)の両方が必要でしたが、動物実験にはコストやかかる時間、人と動物との差異の問題があり、正確な予測が難しいという課題がありました。
この課題を解決するため、株式会社VitroVo は iPS細胞由来の神経細胞と最先端の電気信号計測技術(MEAアッセイ) を活用し、より正確でスピーディーな薬の評価を可能にしました。この技術により、動物実験を減らしながらも、人に近い反応を試験管内で再現できるようになり、製薬業界に大きな変革をもたらしています。
今回のインタビューでは、VitroVoの創業者であり、長年この分野の研究をリードしてきた 鈴木郁郎 氏に、VitroVoの技術の可能性、競争優位性、そしてVitroVoが目指す未来 について詳しく伺いました。
Interviewee

株式会社VitroVo
代表取締役 鈴木 郁郎 さん
2008年3月に東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻博士課程を修め、博士(学術)の学位を取得。同年4月から東京医科歯科大学生体材料工学研究所の助教、2010年から東京工科大学応用生物学部の助教に就任。2014年から現在まで東北工業大学工学部で教鞭を執っており、2019年から東北工業大学AiR研究所の所長も務める。理化学研究所バイオリソースセンター創薬細胞基盤開発チーム客員研究員としても活躍中。2023年12月に株式会社VitroVoを設立。
Interviewer
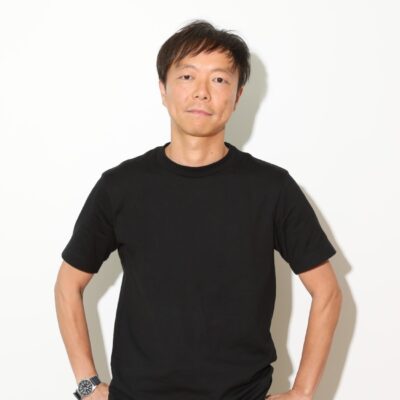
仙台市スタートアップ支援スーパーバイザー
鈴木 修
大学在学時にマーケティング及びEC領域で起業。その後、株式会社インテリジェンスの組織開発マネジャー、株式会社サイバーエージェントの社長室長、グリー株式会社のグローバルタレントディベロップメントダイレクターを経て、2014年に株式会社SHIFTの取締役に就任し国内及び海外グループ会社全体を統括。2019年には株式会社ミラティブでのCHRO(最高人事責任者)、2021年からはベンチャーキャピタルDIMENSION株式会社の取締役兼ゼネラルパートナーに就任。2013年TOMORROW COMPANY INC. / TMRRWを創業し、アドバイザーや社外取締役として、経営や組織人事の側面からスタートアップへのIPO支援や上場企業へのチェンジマネジメントを支援。国内外でのエンジェル投資実績も多数。2023年仙台市スタートアップ支援スーパーバイザーに就任。
─それではまずは、事業内容について教えていただけますでしょうか?
株式会社VitroVo代表取締役の鈴木郁郎です。私たちの社名にあるvitroは、よくin vitroと言われるように、「試験管内の」培養細胞で実験する時に使われる言葉です。一方、in vivoは、動物など生体そのものを使って試験をすることです。
医薬品開発の過程で、化合物の効果や特性を調べる際、人への投与は最終段階の治験でしか行われません。まずはin vitroの実験から始め、次にin vivoつまり動物実験を行いますが、当然そこには人と動物の差異や大動物実験のコストと時間など、多くの課題があります。
私たちが行っている事業は、iPS細胞由来の神経細胞を使い、in vitroでありながら高い精度で化合物の効果や特性を予測する技術です。お皿の上での予測が、人の生体に使用した場合の反応と一致するように、という意味を込めて、vitroとvivoをつなげ、VitroVoという社名にしました。

─高い精度で予測するために、具体的にどのような技術が使われているのでしょうか?
技術としてはMEA(マイクロ・エレクトロード・アレイ)というものになります。細胞の培養をするためのチップに微細な電極が埋め込まれており、細胞の電気信号を計測できます。例えばヒト由来の脳の神経細胞を培養すると、細胞の電気活動が波形となって映るようになっています。この計測結果を指標に、化合物の効果や毒性を評価することができます。
私はこのMEAの研究を2003年頃から行っていて、20年以上この技術に携わってきました。当時は培養細胞の電気活動を測定しても何がわかるのか、直接動物に電極を挿入して生体のレスポンスを取らなければ意味がない、と懐疑的な見方が強い時代でした。
しかし、2006年に山中伸弥先生がiPS細胞を発見したことで状況が変わりました。iPS細胞は人の細胞ですから、様々な細胞に分化させることができ、創薬や再生医療への応用が期待されます。私たちは、世界で初めてiPS細胞由来の神経細胞でMEA計測を行うことに成功し、2013年に発表しました。これにより世界中の細胞メーカーから、自分たちが作製したiPS細胞の機能評価をしてほしいと依頼が止まないありがたい状況となりました。
─研究の土台があった上でiPS細胞の発見による環境変化の後押しもあり、グローバルで急激に大きな展開が広がったのですね。
はい。iPS細胞を使ったMEAアッセイの認知が広がったことで、CSAHi(ヒトiPS細胞応用安全性評価コンソーシアム)という、大手製薬会社が集まる組織の神経チームで発表や主導もさせていただきました。そして大手製薬会社との共同検証や個別の案件も増えてきた結果、これだけニーズがあるのなら事業化すべきだと考えたのです。
大学の研究室は、論文が書けるような研究をするのが本来の役割です。その意味で、企業の非開示案件を扱うことは、大学の研究とは切り離すべきと考えて、東北工業大学としては初の大学発ベンチャーとしてVitroVoを立ち上げることになりました。現在では、CSAHiの事務局もVitroVoが担当しています。
─国際的なプロジェクトにも参画されていらっしゃるとのことですが、それについても少し教えていただけますか?
FDAと緊密な関係にある国際機関のプロジェクトにも参画して、データの解析を担当したり、OECDでも化学物質の安全性評価に関するガイドラインの策定に関わったりしています。最近の米国疾病センターの報告では、33-34人に1人が自閉症になっているとされ、精神疾患の増加が社会課題になっています。これには神経に対する化学物質の影響も考えられるんです。こうした状況下で、神経細胞のMEAアッセイの結果もガイドラインに盛り込まれる方向で検討が進んでいます。

─非常に専門的かつ最先端の分野ですので、私の理解を確認できればと思うのですが、これまでどうしても動物実験を経る必要があった創薬開発の分野で、スピーディーに、低コストで、精度の高いin vitroの化合物実験が、iPs細胞の登場と御社のMEAアッセイによって可能になったという理解でよいでしょうか?その御社の技術の優位性についても解説していただけますか?
そうです。細胞の電気的な活動を測ることで、予測精度が格段に上がったということになります。例えば、人体の細胞がある化合物に触れると痙攣が起きてしまうとします。これがもし臨床で発生したら大変なことで、製薬企業にとって重大な問題です。もちろんその薬品の開発は中止となり、大きな時間とコストが無駄になってしまいます。
しかし、私たちのアッセイではそのような重篤な結果をもっと早い段階で見極めることができる。例えばその化合物の脳内での濃度について、私たちが計測した結果と、動物実験をした結果とが、見事に一致することがわかりました。
また、私たちは機械学習も導入してきました。神経細胞は非常に速い電気活動と複雑な神経ネットワークを展開しているため解析が難しく、どの手法が最適か絞り込むのにも時間がかかります。そこに機械学習の手法を取り入れています。
またある化合物が、既知のどの化合物に近いかも機械学習で素早く判別できます。これにより、例えば体の特定部位の癌細胞をターゲットとする薬が、体内に入ったときに、脳などのターゲット部位以外の場所で思いがけない作用をしてしまうリスクを見つけられたり、わからなかった作用メカニズムが同定できたりしますね。その情報をもとに化合物を改良すれば、より効果的な創薬に繋がっていくと考えています。
─現時点でもかなり精度が高い技術が完成されているようにも見受けられますが、これからのさらなる技術開発はどんな方向性で考えていらっしゃいますか?
私たちは現在大手電機メーカーと組んで、世界最高スペックのCMOS技術を開発中です。従来のMEAは16電極でしたが、新しい技術では24万電極を搭載して細胞の微細な電気信号を取得できるようになります。例えば心臓のネットワークが電気的に活動する様子を、数ミリ秒単位というこれまでの光計測では捉えられなかった速い動きでイメージングできるようになり、より詳細な情報が得られるようになるはずです。
また、MPS(マイクロ・フィジオロジカル・システム)というチップの上に臓器モデルを作製する新しい分野にも取り組んでいます。例えば痛みは、手で感じた刺激が末梢神経を通って脊髄を経由し、脳に伝わることで感じるものですが、このような人体内部のプロセスを1つのチップ上で再現することもできるようになるんです。
―MEAアッセイの技術自体の精密さをベースに御社がこれまで受託してきた実績の蓄積が活用され、しっかりと高く評価されていますね。
長年の技術とノウハウの蓄積により、サンプルの作製方法、計測技術の向上、データ解析手法の開発などの面で、私たちは世界をリードする立場にあると考えています。やはりサンプルと細胞をどれだけたくさん扱ってきたか、知見がどれだけあるかがとても大きいでしょう。知財も多数保有しています。このような取り組みにより、製薬企業からの受託試験を中心に、最近では飲料メーカーや食品メーカーからも、激化する機能性食品の開発のための化合物の評価依頼をいただくことも増えてきました。世界中の細胞ベンダーと繋がりがあることで、私たちは細胞分析のノウハウも蓄積でき、メーカーも細胞を売ることができるというまさにwin-winのパートナーシップが構築できています。

―このステージですでにマネタイズもできており、順調に事業としてグローバルで発展していることは素晴らしいです。質問の切り口が変わりますが、大学発ベンチャーであるということをふまえて、ここに至るまでの背景を、鈴木さんが研究を志した辺りの頃から伺ってもよろしいでしょうか?
私は北九州出身で、母が中学の教員で父が新日鐵の研究職でした。母親は非常に教育熱心で、夏休みも課題をとにかく全部やり切る、地獄のような忙しさでした。
大学、大学院では生物物理を専攻しました。大学院の頃、MEA研究の先駆者の先生から声をかけられて、非常に短期間でデータをとり論文を書く機会がありました。修士1年で4本くらい論文を書き、修士2年で結婚をしたので、博士課程に進む時にはヒモのような状態でしたね(笑)。その後は日本学術振興会の特別研究員として研究を続けるなど、研究をするためにとにかく申請書を出し続けました。本来学生のためのものではない助成金への申請も挑戦しましたし、MEAを扱う会社に、自分の実験用のデモをしてもらうためにコンタクトをとったりしていました。ちなみにその時の会社とは今でも関係が続いていて、やはり人との繋がりがあって、成果を出していけたという形です。
─その後、東北工業大学の教員に就任され、現在はVitroVoの代表取締役でありながら大学院工学研究科の教授でいらっしゃいますね。どのような過程を経てこられたのでしょうか?
博士までの研究は「0から1」を生み出すような研究でした。しかし、人類が成し得てきたことを組み合わせたり、まだ人類が到達し得ていないことを補完する「1から2」の研究、それから「2から3」となる応用研究や実用化研究など、研究にはいろいろなタイプがあると思います。私の場合、東北工業大学に来てからは、実用化研究の方にフォーカスしましたので、実際の製薬会社のニーズを捉える形で研究を活かしたり、また、実用化を踏まえてもう一度基礎研究に戻ってくるなど良いフィードバックを得ながら、事業化できたのだと考えています。
―一般的に、大学の先生は比較的静かに着々と研究を進めている方が多い印象ですが、お話をお伺いしていると、鈴木さんは研究と事業ないしは研究と社会実装の両軸を自然と考えならその両軸成立に向かって柔軟にタフに実行されてきたような印象です。世の中の大学発ベンチャーについて、率直にどうお考えになりますか。
着任した当時は、私も研究だけをする気でいたんです。研究者となる以上、教授のポストをゴールと考えるのは自然なことですし、対外的にはとてもメリットのあるポジションです。それに、私自身起業の仕組みもよく知りませんでした。しかし結果的には、大変ながらも私は本学初の大学発ベンチャーを立ち上げることになった。規定作りから始めて、大学教授と会社代表をすることの、利益相反の問題なども含めて多くの協議を重ねてきました。
この辺りは問題にされることが多い部分ではありますが、利益相反にこだわることが将来的に日本の生産性を上げるのに効率的かどうかは、疑問があるところです。大学発ベンチャーを国が奨励するなら、よりシステムが緩和されるべきだと思います。その方がサイエンティストを目指す人たちにとっても夢がありますよね。大学にはたくさんの雑務があり、待遇も良いことばかりではないですし、若者が大学教員になりたいとは思わない世の中になっていると思いますね。
―現状の日本においては、大学教授をしながら事業をするということに対する柔軟な環境や制度や仕組みや文化が無く、そして適切なインセンティブ構造も無いなかで、鈴木さんはどのようなお考えで大学と事業の両立を実現されているのでしょうか?
だから、私はとにかくたくさん働くしかありません(笑)。私は大学での仕事は仕事でしっかりと行い、基礎的な研究や試験などは怠らないようにしています。一方で、企業活動では研究者と研究者の関係で仕事ができるため、スムーズに進められる面もあります。受託研究の実績を積み、製薬会社とのパートナーシップを作ってきたことで、VitroVoは小さなベンチャーながら、ゼロからのスタートにならずに済み、効率的に事業を展開することができました。また実働スタッフも、研究員と兼業で自然と集まっています。
─今後の大学発ベンチャーの発展についてのお考えをお聞かせいただけますか?また起業をする学生についてはどう捉えていらっしゃいますでしょうか?
研究として素晴らしいものはたくさんあっても、ビジネスとして成立するかというと難しいものが多いのは事実だと思います。事業化する上では、研究者としてのこだわりに固執するのではなく、勇気をもって捨てることも大切だと感じています。実用化、ニーズに基づいて基礎を進めていくことも大事で、究極を求めにいくよりも、もっとスタンダードに、実用化の目的が達成される方が、ビジネスの種となり得ます。
学生起業については、本学では少ないのが現状です。いわゆるアントレプレナーシップ、自分で自立して飯を食う、という姿勢はもっと生まれてほしいと思っています。
─起業することは容易ですが、その後しっかりと会社を成功させるためにハードシングスを乗り超えていくこと難易度が高く、成功確率は限りなく低い確率ですので、大学の業務が中心の中で片手間で経営し会社を成功に導くことは不可能に近いことだと思います。大学発ベンチャーの在り方、そしてそのベンチャーを率いる大学教授の在り方、鈴木さんはその一つのロールモデルですね。最後に、今後の構想についてお聞かせください。
今はまだIPO、M&Aなどは考えておらず、受託、それも海外展開に注力しようとしています。実際に海外の製薬企業との話も進んでおり、海外に対応できるようウェブの構築なども進めています。また、MEAアッセイの実績を活かして、受託事業だけでなく、私たち自身が創薬に関わるということも今後の課題の一つです。
ただし、無理な拡大は考えていません。著名人を役員に迎えるとか、急いで投資を受けるといった提案もありましたが、納得できないことはしないと決めています。まずは固く売り上げを立てる。素人でも納得できる判断を心がけ、着実に前進していきたいですね。